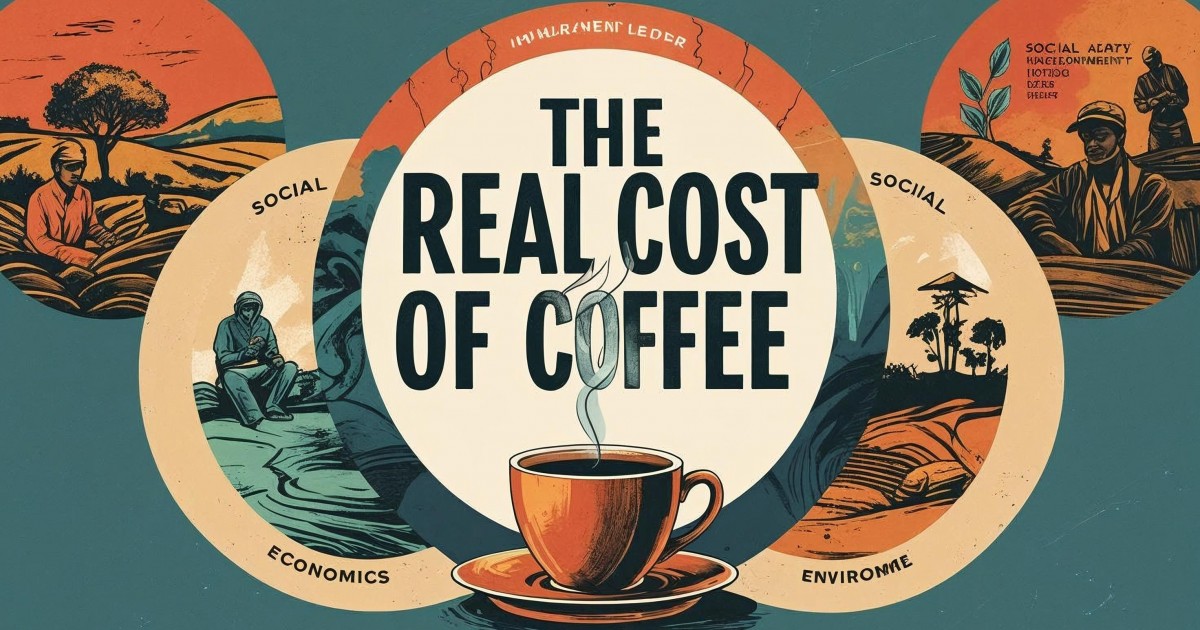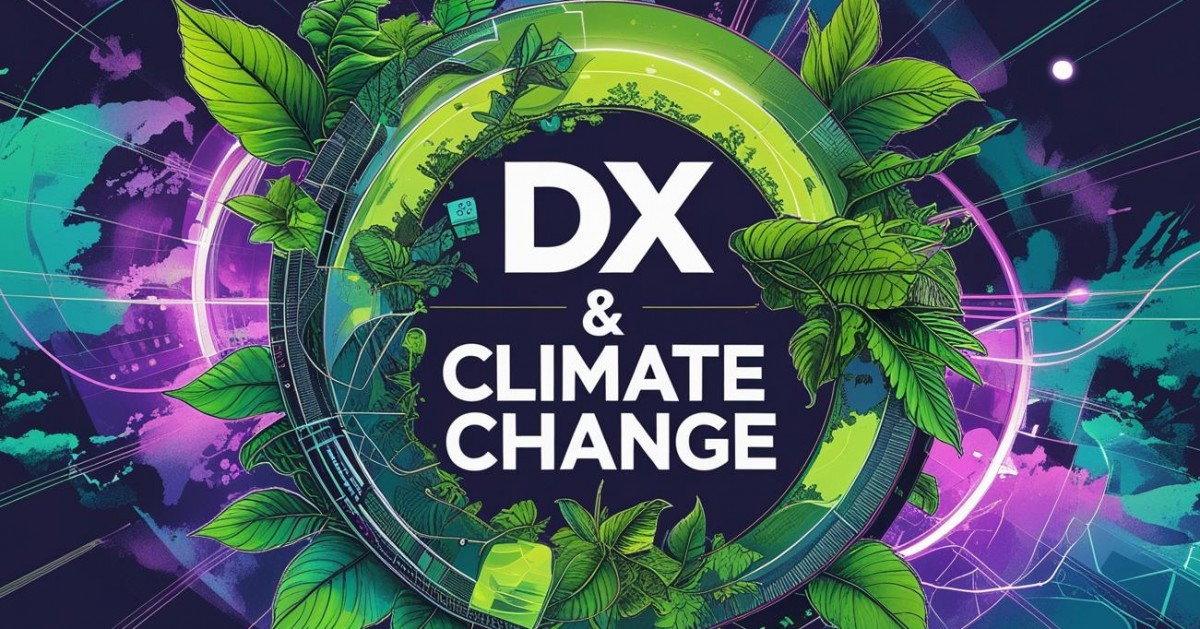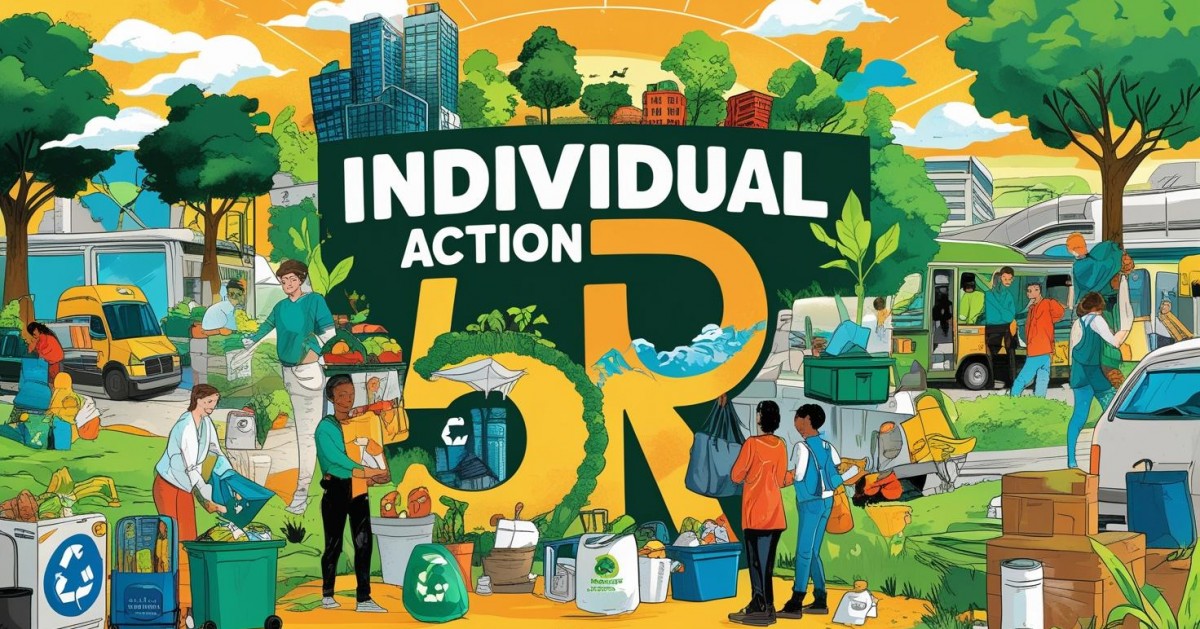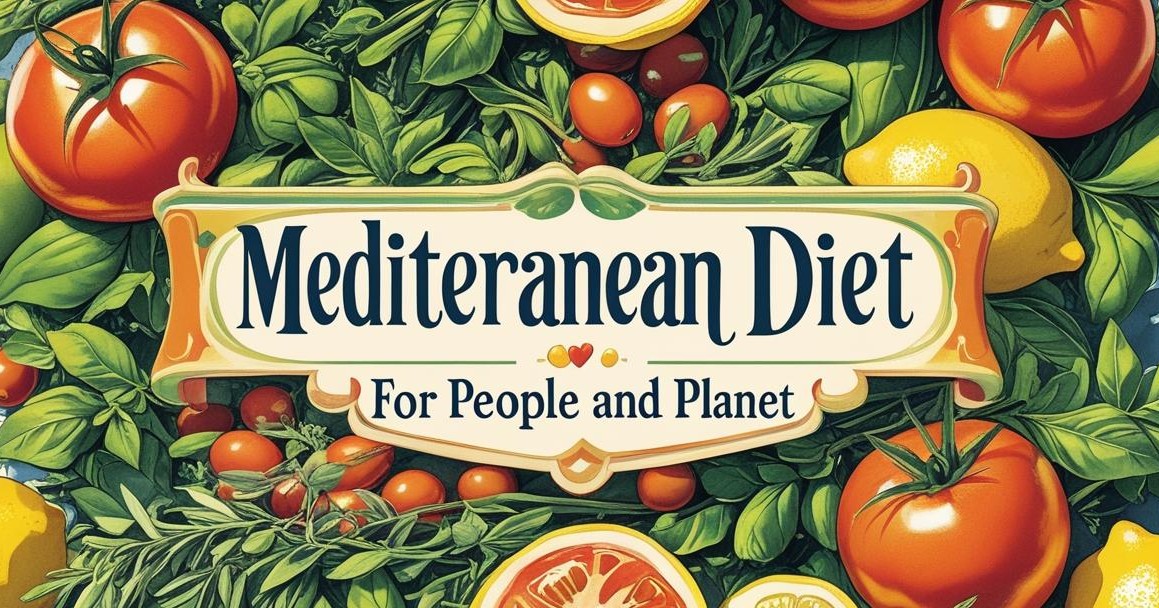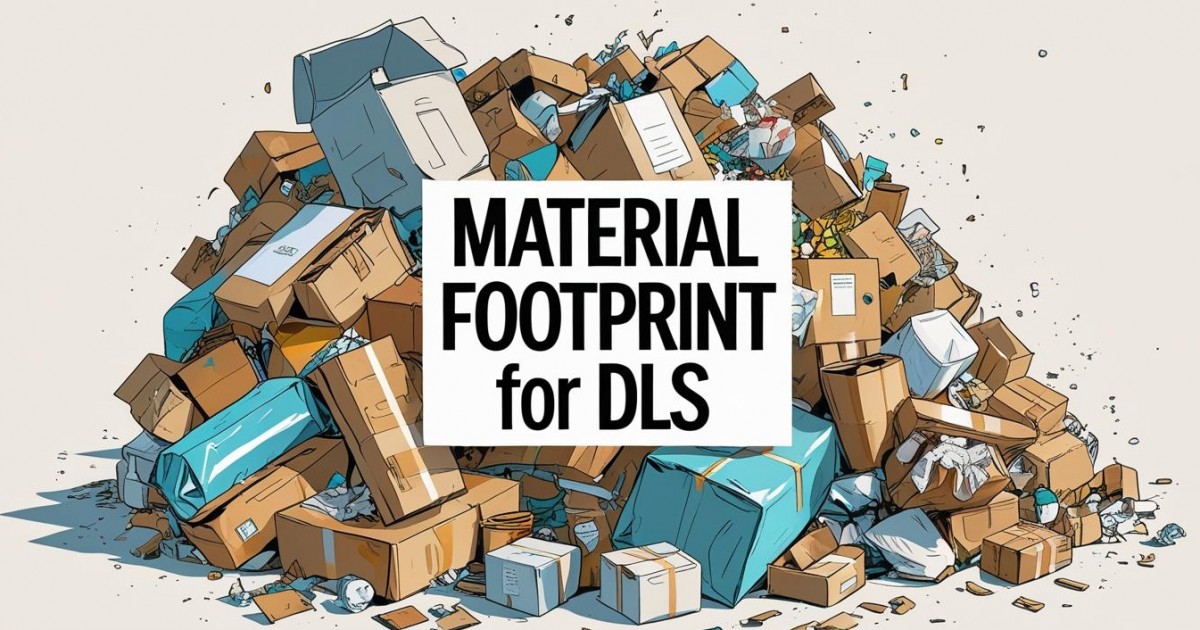バイオエコノミーとSDGsは仲良くできるのか
さぁ4月も2週目です。僕は先週、1限が8時からなのに、7時半に起きてギリギリで授業に行っておりました (正確には、2回遅れています)。なので、今週は7時に起きよう〜ということで、今日は7時6分に起きまして、良い朝でございます。
良習慣を続けて、レターもたくさん書いていきたいですね〜と。
今回は、ヨーロッパにおけるバイオエコノミーとSDGsの関連性を分析してみたって論文です(Anne, 2025)。本論文でも書かれておりましたが、バイオエコノミーってのは必ずしも循環的であったり持続可能だったりする訳ではないんですね。シンプルに「化石燃料に依存しない経済を〜」ってノリで、ゴリゴリに技術開発した結果、それ自体環境負荷が高いよねっていうマイナス点も、まぁあるっちゃある訳です。
そこで、泣く子も黙るSDGsと関連性を比較してみて、お互い高め合ってますか〜と、意外と仲悪かったりするんですか〜というのが見えてくるよということです。
それでは、いきましょう。
バイオエコノミー 10原則
バイオエコノミーの解説記事で挙げてなかったので、ここで復習としてもちゃんと取り上げときましょう。この指標フレームワークは、2019年にFAOが10の原則と24の基準を設定しており、持続可能で循環的なバイオエコノミーへの移行を監視するための包括的なツールです。
-
全てのレベルで食料安全保障と栄養を支える
-
天然資源の保全、保護、強化を確実にする
-
競争力と包括性を備えた経済成長を支える
-
コミュニティをより健康で持続可能にし、社会と生態系の回復力を高める
-
資源とバイオマスの利用効率の向上に頼る
-
責任ある効果的なガバナンスメカニズムが支える
-
既存の関連知識と実証済みの健全な技術と優れた実績を有効に活用し、適切な場合には研究と革新を促進する
-
持続可能な資源と市場慣行を活用し、促進する
-
社会のニーズに応え、持続可能な消費を促進する
-
あらゆる関連分野とあらゆるレベルの利害関係者の協力、連携、共有を促進する (FAO, 2021)
経済に関して、より具体化して研究者・政治家向けにガイドラインを出している感じですね。特に「5. 資源とバイオマスの利用効率向上」なんかは、めっちゃ的絞ってますね。
SDGsとバイオエコノミーで、共通点はありそうなものの、対象とするペルソナの設定がそもそも違うような、という痒いところを分析した訳ですね、おもしろめ。
研究方法は統計分析で、BEの10原則すべてと基準の約80%をカバーする1,382の指標を特定し、SDGs17の目標と、141のターゲット、そしてさらに細分化された2205の指標を包括的にカバーしております。こりゃ人間にはできません。
結果、バイオエコノミーがSDGsに55%の相乗効果(シナジー)をもたらしている一方で、45%にトレードオフがあることがわかりました。
シナジー
BE→SDGsのシナジー 上位5つ
-
BE10 (協力)→ SDGs7 (クリーンエネルギー)・12(責任ある生産と消費)
-
BE5 (資源効率) → SDGs13 (気候変動)
-
BE7 (技術革新) → SDGs13 (気候変動)
-
BE9 (持続可能な消費) → SDGs7 (クリーンエネルギー)
-
BE10 (協力)→ SDGs12(責任ある生産と消費). (Anne, 2025)
と、バイオエコノミー原則の「10. あらゆる関連分野とあらゆるレベルの利害関係者の協力、連携、共有を促進する」がSDGsの中でも、特にSDGs7(クリーンエネルギー)、12(責任ある生産と消費)、15(陸の豊かさ)、17(パートナーシップ)に強いプラスの影響を与えていると。
バイオエコノミーそれ自体とはあんまり関係なさそうな、社会的な原則が共通点として炙り出された感じですね。
他には、やはりバイオマスに力を入れていることから、7番のクリーンエネルギーだったり、13番の気候変動に相互作用がある訳ですね。
SDGs→BEのシナジー 上位5つ
-
SDGs 15 (陸の豊かさ) → BE8 (持続可能な資源)
-
SDGs 11 (持続可能な街づくり) → BE8 (持続可能な資源)
-
SDGs 5 (ジェンダー平等) → BE8 (持続可能な資源)
-
SDGs 10 (クリーンエネルギー) → BE10 (協力)
-
SDGs 15 (陸の豊かさ) → BE3 (競争的). (Anne, 2025)
こっちは、社会基盤を整えることで、バイオエコノミーに提供するバイオ資源が持続するといったシナジーですね。
トレードオフ
BE→SDGsのトレードオフ 上位5つ
以下は、バイオエコノミーを進めることによって、SDGsの達成に悪影響を与える可能性がある項目です。
-
BE4 (回復力)→ SDGs16 (平和)
-
BE8 (持続可能な資源) → SDGs2 (飢餓ゼロ)
-
BE3 (競争的) → SDGs12 (責任ある生産と消費)
-
BE1 (食料と栄養) → SDGs7 (クリーンエネルギー)
-
BE1 (食料と栄養)→ SDGs13(気候変動). (Anne, 2025)
ここで特筆すべきは、バイオエコノミーが気候変動に悪影響を与える可能性があるということです。本論文の中では、バイオエコノミー原則は、気候変動に対して最も強いプラスとマイナスの影響を持っていると論じられています(Anne, 2025)。
というのも、バイオエコノミーの実践は、化石燃料の燃焼によるCO2排出量削減に大きなプラスの効果があるものの、土地被覆の変化、集約的な農業慣行、広範囲にわたる灌漑など、バイオ資源を作るための変化が、地中に固定された炭素を放出し、気候変動に悪影響を与える可能性があるのです。いやぁ複雑な問題だ。
SDGs→BEのトレードオフ 上位5つ
続いて、SDGsを進めることによって起きるバイオエコノミーへの悪影響です。
-
SDGs 1 (貧困ゼロ) → BE8 (持続可能な資源)
-
SDGs 13 (気候変動) → BE8 (持続可能な資源)
-
SDGs 12 (責任ある生産と消費) → BE6 (ガバナンス)
-
SDGs 2 (飢餓ゼロ) → BE10 (協力)
-
SDGs 8 (経済成長) → BE6 (ガバナンス). (Anne, 2025)
けっこう因果関係がわかりにくいことに加え、あまり説明も無いので困りようです。筆者はSDGs9の下位目標(産業、イノベーション、インフラ整備)とBE基準3.3(農村経済と都市経済のレジリエンス)についてマイナスの影響を論じています。
SDGs9.1と9.4はインフラのアップグレードと産業の持続可能性向上に関するものですが、これを進めることは、インフラの拡張を優先を意味する。一方で、BE原則3.3では農村経済と都市経済の結びつきを強くしましょうと言っている。これは、より新しくしてインフラを広げようって観点と、地産地消のバイオ資源を大切にしようって観点でバッティングするという訳です。
SDGsのターゲット9.3による様々なセクターにおける経済活動の拡大と激化が、バイオエコノミーの気候効果を打ち消すような、環境へのマイナスを生み出す可能性があるよと指摘しております。
まとめ
論文の中ではそれぞれの関連性についてパーセンテージで表されており、シナジーは10~30%、トレードオフは大体が10%以下なので、やはりシナジーの方が大きいのは間違いない模様。しかし、場合によって相反する場合もあるのは確かなので、「これはバイオエコノミーの政策だから良い感じだあ!」と無批判に受け入れるのは危ないよということですね。
-
バイオエコノミーの、あらゆるセクターとの協力の姿勢はSDGsを強化する
-
SDGsの、社会基盤形成はバイオ資源を持続可能にする
-
バイオ資源生産の拡大が、気候変動にマイナスを与える可能性がある
-
SDGs的な産業拡大が、バイオエコノミーのバリューチェーンの足枷になる可能性がある
参考文献
-
Anne Warchold, Prajal Pradhan, Bioeconomy and Sustainable Development Goals: How do their interactions matter?, Geography and Sustainability, 2025, 100293, ISSN 2666-6839, https://doi.org/10.1016/j.geosus.2025.100293.
-
FAO. 2021. Aspirational principles and criteria for a sustainable bioeconomy. Rome.
すでに登録済みの方は こちら