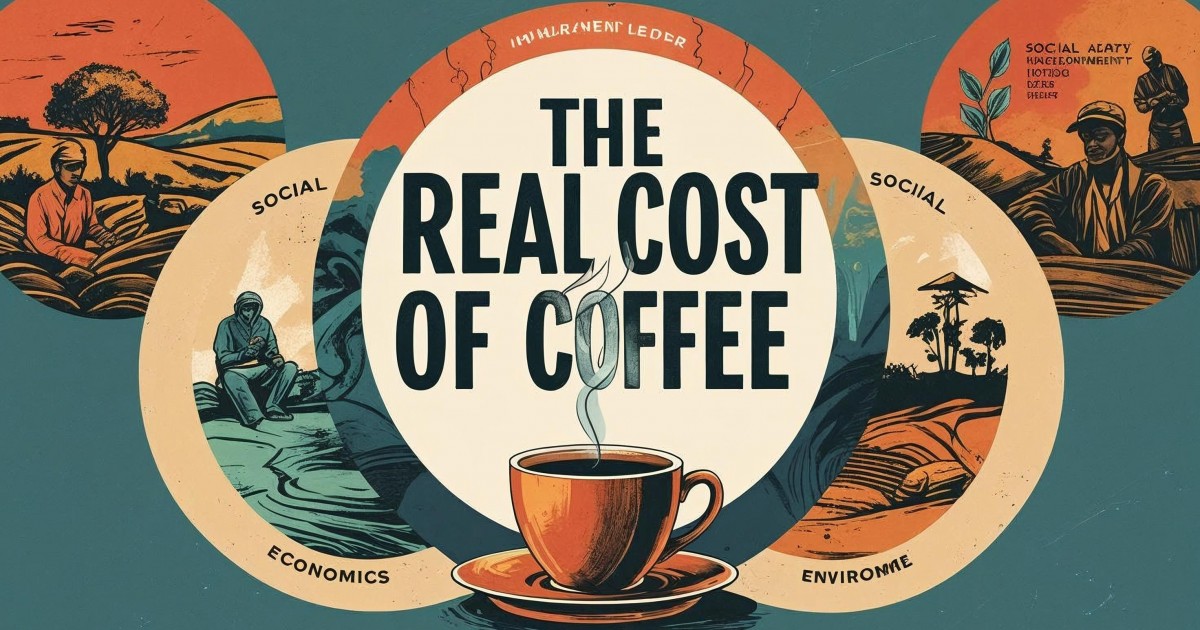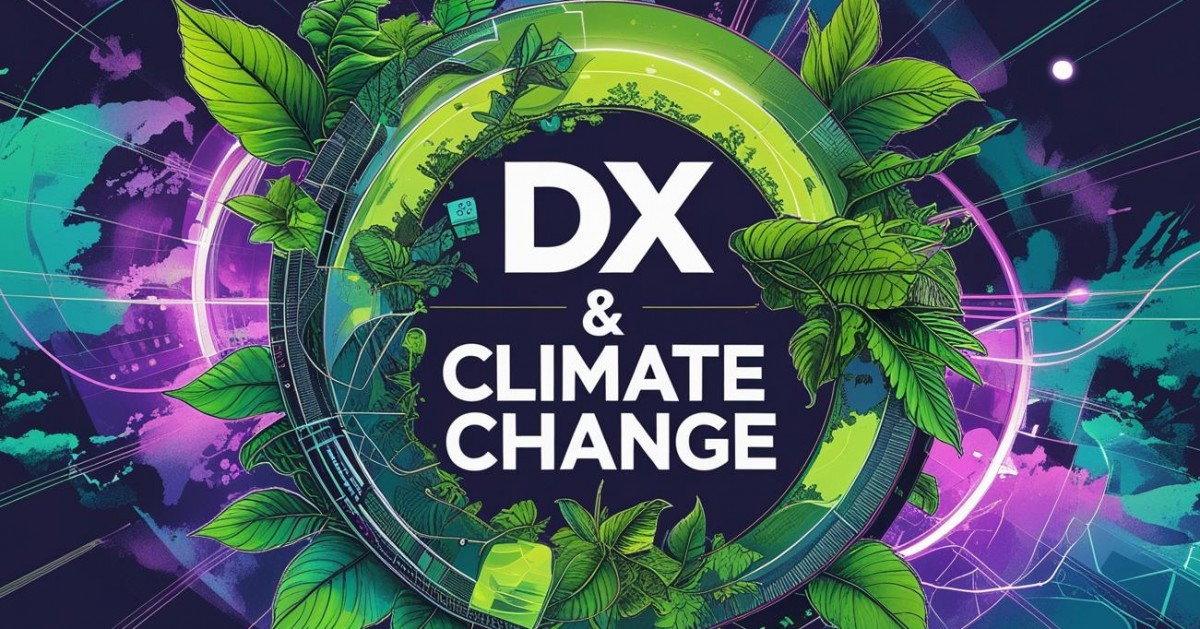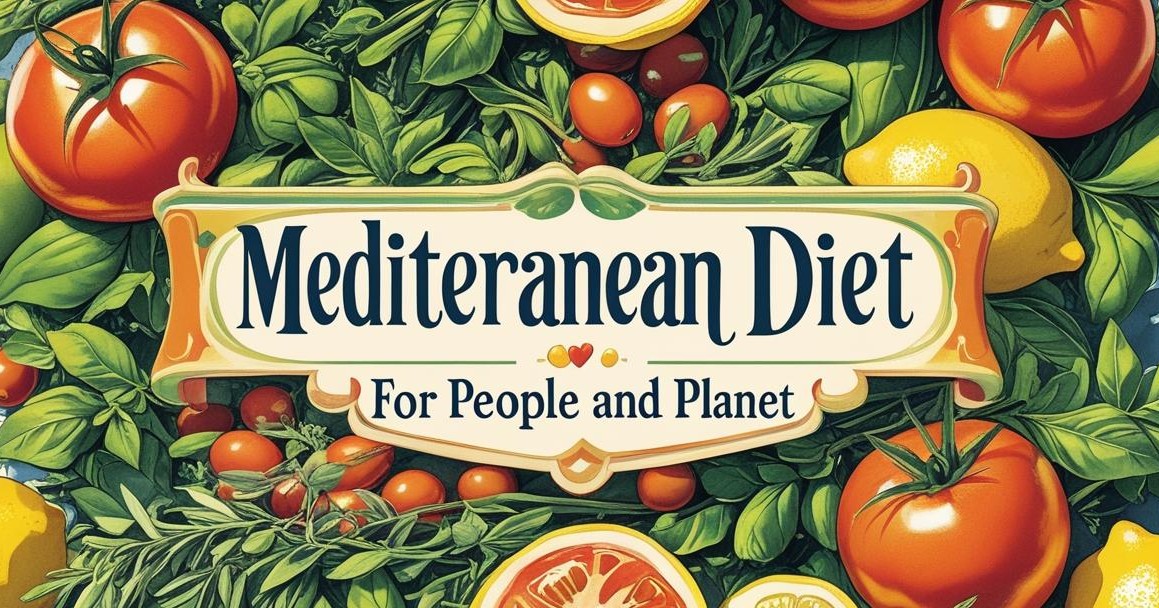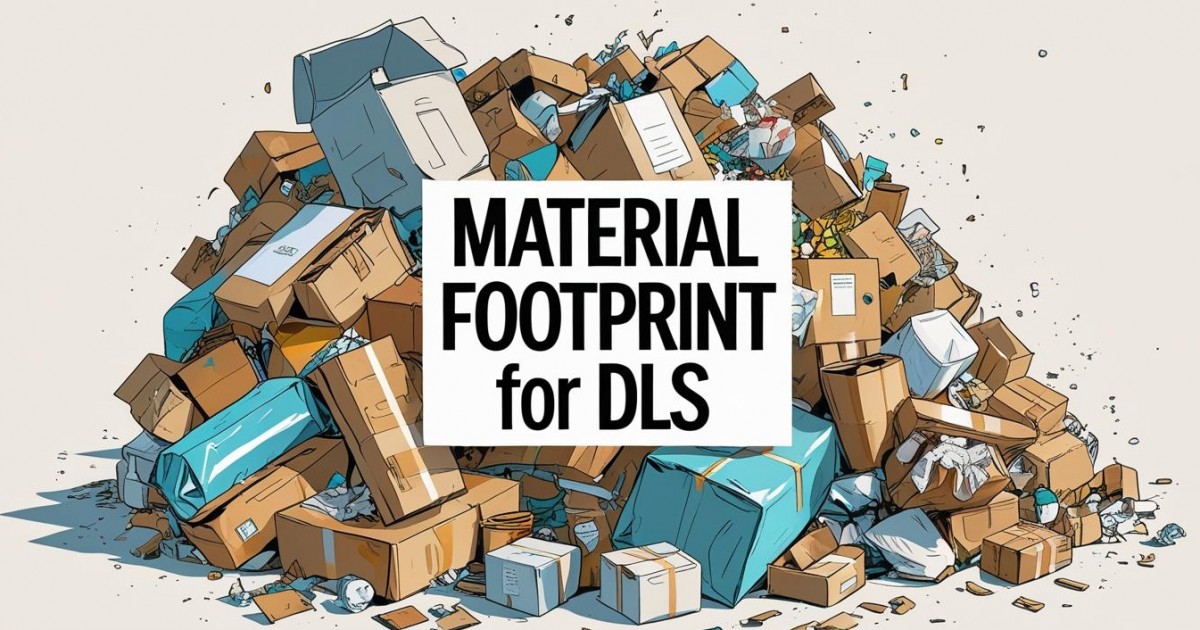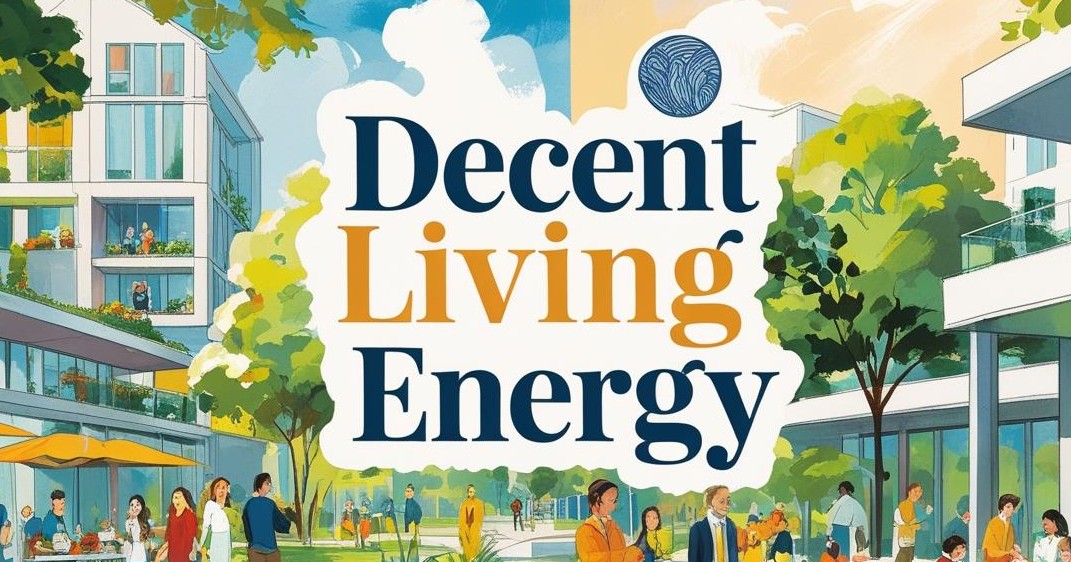個人レベルでの気候変動 緩和策 "5R"
テュービンゲン、フライブルクとドイツ南西部を旅行してきました。エコ住宅を回ったりヴィール原発建設が予定されていた場所をめぐり、ドイツの環境意識を現場で感じられました。ヴィールでは、70年代に座り込みで反対運動をしていた学生たちに炊き出しでパンとスープを持って行ってあげてたというおじさまともお話しできて良かったです。ドイツのアクティビズムが活発である理由に触れられた気がします。
さて今回は2025年7月に発表された論文、「個人レベルでの気候変動緩和:5Rを活用した温室効果ガス排出抑制」を読んでいきましょう(Hiral Jani & Ankit Bhojak, 2025)。
「今日から個人でできること」は、多くのメディアで取り上げられたり、ワークショップなどで人気なテーマですが、「アメリカや中国がCO2減らさないと意味ない」なんて冷笑的な意見もありますね。
そこで、この論文は「個人の行動は無力だ」というシニシズムを跳ね除け、僕たちの日常がいかに地球の健康に直結しているかを、具体的に示してくれております。「5R」を学んで、暮らしをひとつずつ変えていきましょう~。
すべての行動の土台となる「5R」
「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」という言葉はわかりますよね。ただ、この論文が提唱するのは、それをもっと進化させた「5R」というフレームワークです。
-
Refuse(リフューズ):断る ← "NEW"
-
Reduce(リデュース):減らす
-
Reuse(リユース):再利用する
-
Recycle(リサイクル):資源として再生する
-
Recreate(リクリエイト):再創造する ← "NEW"
この「5R」は、いわゆる「サーキュラーエコノミー」的な、ゴミ削減のスローガンに留まらず、温室効果ガスの排出を減らすための行動指針です。3Rの前後に1つずつRが追加されて5つになっております。
特におもしろいのは、5番目の「Recreate(再創造する)」ですね。これは、マイナスをゼロにするだけでなく、より良い社会や生態系をさらに積極的に創り出していくという、ポジティブな概念です。
それでは、ここから5つのステップを、僕らの日常生活に落とし込みながら、ひとつずつ見ていきましょう。
1. Refuse (断る): 結局これが1番
まず初めに、いわゆる3Rの前に追加されているのがこのリフューズです。一言でいうと、「何をするか」ではなく、「何もしない」ことが1番環境に良いってことです。
川の下流で水をきれいにすることも大切ですが、そもそも上流から汚染物質を流さないということが、はるかに効率的で根本的な解決策だという訳です。
今回は「個人でできること」なので、アクションプランをダダダっと挙げていきます。
<Refuse アクションプラン>
-
「無料」を断る:コンビニのレジ袋、プラスチック製のスプーンやフォーク、ホテルの使い捨てアメニティ。
-
過剰包装を断る:野菜が一つひとつプラスチックで個包装されていたり、小さな商品が大きな箱に入っていたり。ドイツ人が日本に来た時に包装が多すぎるって驚いてました。
-
不要なエアコンの使用を断る: 少し涼しい日なら、窓を開けて自然の風を取り入れる。設定温度を1℃見直すだけでも、大きな省エネにつながる。
-
近距離の車移動を断る:健康のためにも、地球のためにも、徒歩や自転車を選ぶ。
-
衝動買いを断る:「安いから」「限定品だから」という理由だけで、本当に必要ではないものを買わない。未来のゴミと無駄なエネルギー消費を防ごう。
Reduce (減らす): 少なく、豊かに暮らす
次のステップは、いつもの3Rに戻って、リデュースです。
なんだか「我慢」のように聞こえてしまいますが、生活に必要なものの「量」を見直すことで、本当に大切なものを見極め、より質の高い、シンプルな暮らしが実現できるのだと自分を騙すことが第1歩です笑。
<Reduce アクションプラン>
-
フードロスを減らす:日本の家庭から出るフードロスの量は、年間1人当たり約48kg。これは、毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているのと同じ。
-
計画的に買う: 冷蔵庫の中身を確認してから買い物に行き、必要なものだけを買う。
-
肉の消費量を減らす: 週に1日「ミートフリーマンデー」を設けてみる。牛肉1kgの生産には、トウモロコシ11kgと水2万リットルが必要。肉の消費を少し減らすだけで、温室効果ガス排出量、水使用量、土地利用を劇的に減らせる。
-
省エネ家電に買い替える: 10年前の冷蔵庫やエアコンを最新のものに変えるだけで、電気代もCO2排出量も大幅に削減できる。
-
LED電球に交換する: 白熱電球をLEDに変えるだけで、消費電力は約85%も削減される。
-
水を大切に使う: シャワーの時間を1分短くするだけで、年間約70kgのCO2削減。
-
モノの量を減らす:「1つ買ったら、1つ手放す」というルールを決める。ファストファッションのサイクルから抜け出し、長く使える質の良いものを選ぶ。
という訳で、ここでも食生活の変化は必須ですね。食生活シリーズはいろいろやってますんで、また読んでください。
Reuse (再利用する): いいものを長く使う
続いても3Rからの登場。一度手にしたものを、使い捨てずに、繰り返し使うリユースです。リサイクルのように、原料に戻すためのエネルギーが不要で、その形のまま使うので環境負荷が低いので、優先順位も高いです。
<Reuse アクションプラン>
-
「マイ〇〇」を相棒にする:マイボトル、マイバッグ、マイカップ、マイ箸で使い捨て文化を卒業。
-
リユース市場を冒険する:新しい服や家具が欲しくなったら、まずはフリマアプリやリサイクルショップを覗いてみる。自分が使わなくなったものを売ったり譲ったりもグッド。
-
修理して使う文化を取り戻す:少し壊れただけで捨ててしまうのではなく、自分で修理してみる。地域の修理屋さんを探してみる。
-
新しい使い方を発見する:着古したTシャツは雑巾に、お菓子の空き缶は小物入れに、ジャムの空き瓶は保存容器に。創造性のトレーニングにもなる。
修理して使う文化に関して、この論文は、インドの「jugaad (ジュガード)」という言葉を引用しております。これは「ありあわせのもので工夫してなんとかする」という創造的な精神です。日本の「もったいない」にも通じる良い文化ですね。ここは江戸時代の日本にも学んでいきましょう。
Recycle (リサイクル): 生まれ変わる
そしてリサイクル。製品をそのまま使うのではなく、いったん資源まで戻して新しいものを作り出すことです。リサイクルプラスチックが身近な例ですね。ただ、リサイクルの過程で資源の質は劣化していくので、無限にできる訳ではないというのは注意点ですね。
<Recycle アクションプラン>
-
分別の達人になる:自分の住む自治体のルールを、もう一度しっかり確認してみる。「ペットボトルのラベルを剥がす」「中を軽くすすぐ」といった一手間が、リサイクルの質を左右する。汚れてるプラスチックは焼却される。
-
見過ごされがちな資源を救う:スーパーや公共施設に設置されている、小型家電、電池、インクカートリッジなどの回収ボックスを活用する。貴重なレアメタルが含まれている。
-
リサイクル製品を選ぶ:「再生紙100%」や「リサイクルプラスチック使用」のラベルがついているものを選ぶ。
回収ボックスの場所は一度把握しておくと、家に使用済み電池を溜めることも無くなるので大事です。最近ではペンの回収とかもありましたね。家に使ってないペンがたくさん眠ってたりするのももったいないポイントですよね。
Recreate (再創造する): 未来を、より良く創り出す
最後の「R」は「Recreate(再創造する)」です。かっこいい。これは、環境負荷を減らすだけでなく、積極的にプラスを生み出し、より豊かで健康な生態系や社会を「再創造」していこうというアクションです。これはなんだかワクワクします。
<Recreate アクションプラン>
-
コンポストを始める: 生ゴミをコンポストで堆肥に変える。豊かな土壌を「再創造」し、いのちも「再創造」できる。
-
家庭菜園やプランター栽培: ベランダでハーブやミニトマトを育てる。食料生産のプロセスを体験し、身近な生態系を「再創造」できる。
-
植林活動に参加する: 地域の植林イベントや、NPOの活動に参加してみる。木を植えることは、CO2を吸収し、生物多様性を高め、豊かな森を「再創造」する。
-
シェアリングサービスを活用する: 車が必要な時だけカーシェアを利用する。たまにしか使わない工具は、近所の人と共有する「ツールライブラリ」を利用する。モノの「所有」から「共有」へ。地域のつながりを「再創造」する。
-
地域の活動に参加する: 地域の清掃活動や、修理の技術を教えあう「リペアカフェ」に参加する。人とのつながりの「再創造」。
-
学び、伝える: 気候変動について、信頼できる本やドキュメンタリーで学んでみる。そして、その知識や危機感を、家族や友人と対話してみる。正しい知識と意識のネットワークを「再創造」する。
-
声を上げる: 公共交通機関の整備、再生可能エネルギーへの転換、企業の環境配慮などを、政治家や企業に求める「声」を上げ、未来を「再創造」する。
リクリエイトはかなりアクティブで楽しそうですね。特に、地域の人とのつながりを再創造するってのはなかなか面白い。環境のためだと思っていたことが人のためになり、自分のためにもなるという、いい循環ができていますね。
そして学ぶ、伝える、声をあげる、というところまでできれば、共同体感覚も生まれ、いい未来が再創造できそうですね。
まとめ
-
Refuse(リフューズ):過剰包装、自家用車、衝動買いを断る
-
Reduce(リデュース):フードロス、食肉、モノの量を減らす
-
Reuse(リユース):マイボトル、リユースショップ、修理で再利用
-
Recycle(リサイクル):分別、回収ボックスで資源循環
-
Recreate(リクリエイト):コンポスト、植林、地域活動で未来を再創造
もちろん、この論文も、個人の行動で全てを解決できると言っている訳でなく、政策やインフラ、教育といった社会全体のサポートを充実させようと言っております。
しかし、その方向に社会を動かすのも、また僕らの行動と声だということも忘れずにいたいところです。大きな変化も個人小さなうねりから始まるということを意識して、僕もうねっていきます。
余談ですが、『ソフィーの世界(下)』を読んでまして、そこに今回の「個人でできること」に関する良い記述を見つけました。なぜこれらの「個人でできること」をするかの理由を一言でいうと、「自由に生きるため」と言えます。
カントの哲学では、自由意志こそが大切だが、全ては自然の因果律に従っています。何を見るか、何を感じるかといった「感覚的存在」は望む望まないに関わらず押し付けられると。しかし「理性的存在」は、感覚から独立した存在なので、自分で決めた「道徳律」に従った行動をとることができます。人間はその時だけ自由意志を持てると言います。なぜなら道徳律に従うとき、その道徳律を決めているのは自然の因果ではなく、自分自身だからです。
つまり、「丁寧な分別が気候変動を緩和させる」もしくは「気候変動になんら影響をもたらさない」という結果は、自由意志とは全く関係ありません。むしろ、自身が決めた「環境にやさしいことをする」という道徳律に沿っているかどうかこそが重要だという訳ですね。その時だけ、僕たちは自由意志で行動しているからです。
とまぁ、うんちくを話しても仕方ないですが、「その行動が意味があるかどうか」という、行動の結果を考えても仕方ないので、「僕はこの方が気持ちがいい」という行動の理由を、自分の方に置くことが大事だよねというお話でした。
参考文献
-
Jani, Hiral & Bhojak, Ankit. (2025). Climate Change Mitigation at the Individual Level: Harnessing the 5Rs to Curb Greenhouse Gas Emissions. International Journal For Multidisciplinary Research. 7. 10.36948/ijfmr.2025.v07i04.50960.
-
ヨースタイン・ゴルデル(池田香代子 訳),『ソフィーの世界 下』, NHK出版, 2002年
すでに登録済みの方は こちら